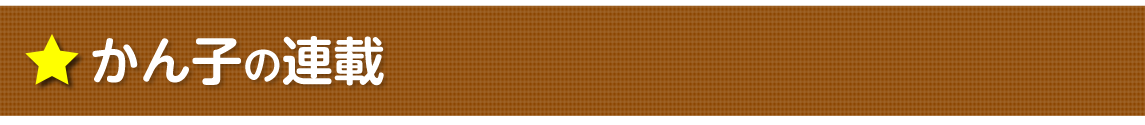☆楽しい学校図書館のすぐに役立つ小話☆彡【司書は椅子に座ってピッとやるだけの人じゃありません。学校司書は忙しいんです。・4-2】
学校司書の桜李桃梨(おうりとうり)さんからの寄稿をご紹介していきます。
小話とは言えない??、学校司書さんの忙しい日々をぜひご覧くださいませ~
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
4-2 整備②
そういえば、折り紙の件も目からうろこでした。
講習会に行ったら、折り紙の紙は練習用なのだから、その折り紙用の安い紙で練習して、折れるようになったら本番はちゃんとした紙で折るものだ、といわれたのです。
折り紙で飾るとなんだか安っぽく見えるなぁ、とはそれまでにもボンヤリ思っていたのですが、なんというか、学校図書館には折り紙を飾るものだとばかり思いこんでいたので、それ以上は深く考えなかったのです。
でもそれからは飾るものはちゃんとした紙で折り、折り紙の紙で折ったものは飾らなくなりました。
それだけでもだいぶ飾り物の印象が、変わりました。
他にも、長期間飾る掲示物を作るときは、画用紙ではなく少し良い紙を使うようになりました。
これはたまたま、学校で余ってた良い紙をもらえたことがキッカケだったんですけど、その紙で掲示物を作ったら、子ども達の目に入りやすくなったらしく、いつになく注目してもらえたのです。
折り紙のことがあったのでこれもそうか、と思い、それからは文具店で売ってるバラ売りしてる少し高い紙、といっても一枚20円とかですけど、の紙で作るようになりました。
そうしたら、それだけで掲示物のレベルが確実に上がったのです。
紙の質、つまり、材料にポイントがあったなんて!
それまでも、貼る内容は考えて書いてました。
バランスとか、書体なども。
でもまさか、それを貼る紙がこんなに大きいとは!
ほんと、目からうろこが落ちました。
その次はカウンターでした。
これも学校あるあるなんですけど、たとえばスーパーでカウンターに穴があいてたり、ヘリが剥がれたりしていたら、普通、使わないですよね?
でも、学校にいると、そういうことを、なんとも思わなくなるのだ、ということにようやく気がついたのです。
その時の学校のカウンターは、天板は鉛筆で真っ黒、横板にも穴があき、ヘリが剥がれている状態でした。
なので、まず天板をメラミンスポンジなどで磨き(つるつるのものなら、たいていこれで綺麗になります)蹴飛ばされて穴があいていたカウンターには(幸い木だったので)ガンタッカーで布を貼りました。
それだけしてもパッとしなかったので、古い縁にはペンキを塗ったところ、本当に光り輝くようになったのです(下のはかまの部分には、黒いプラダンをカットして貼りつけました)。
見違えるようになったカウンターに子どもたちはやはり大興奮して、大喜びしてくれました。
「新しいのを買ったの?!」
や
「先生、きれいになったね!!」
「頑張ったね~!」
とねぎらわれることもー。
自分が子どものときにも思い返せばそうだったな、と思いますが、子どもって、色や形に敏感なんです。
手触りも。
そうして、きれいなものが好きなのです。
なのに日本の学校の汚いことと言ったら。
掃除……は頑張っていると思いますし、手が足りないのも事実です。
公共の施設で定期的にプロの掃除が入らないのなんて学校だけだなんじゃないでしょうか。
カーテンを洗いたくてもドライクリーニング代が出なかったり(いまはようやく、防災カーテンも洗えるようになった商品もあるようになりましたが、ちょっと昔のものは洗濯機で洗えませんでした)危なくて窓ガラス磨きをさせられない設計や、はじめから足場を組まないと掃除できないような建築は先生方の責任ではないと思います。
先生はお掃除が仕事ではありませんから。
でも、そうやって埃だらけになつている学校に慣れてしまっているうちに、ガムテープをベタベタ貼ったり、破けたポスターをそのままにしておいたりするのも普通になってしまったのです。
カウンターって目立つところなんですよねー。
ということで、それからは定期的にカウンターの天板は磨くようになりました。
やっぱり居心地いい空間は、キレイが1番です!
カウンターに気がついてからは、とりあえず図書館だけでも、と思い、もしここがお店だったら、もしここがホテルだったら、を自分の基準にするようになりました。
お金があるわけではないので、最高、にはできませんが、お金をかけないところでは最善、を目指したいと思います。
2025/07/10 更新