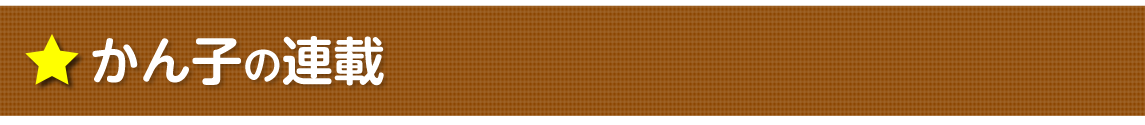☆楽しい学校図書館のすぐに役立つ小話☆彡【司書は椅子に座ってピッとやるだけの人じゃありません。学校司書は忙しいんです。・4-6】
学校司書の桜李桃梨(おうりとうり)さんからの寄稿をご紹介していきます。
小話とは言えない??、学校司書さんの忙しい日々をぜひご覧くださいませ~
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
4-6 長期休みの間の仕事 ①夏休み前まで
学校司書は毎日、駆け抜けるような忙しい日々を過ごしています。
なにせうちなどはお客さまが毎日650人いらっしゃるのですから、繁盛しているコンビニ並みに忙しいのです。
また、 学校司書だと言うと
「休みが多くていいわね」という反応が返ってくることが多いのですが、学校は役所と同じスケジュールで動いているので、お盆とお正月の休みは役所と同じにありますが、先生がたも私たちも子どもたちのように長期の休みがとれるわけではありません(かつては一ヶ月まるまる休みになり、先生がたは自分の研究やら、で動けていた時代もあったようですが、今はそんなところはないでしょう)。
むしろその時期にやらないといけない、普段とは違う仕事が山積みになります。
たとえば、春休み……。
先生がたはもし移動になれば自分の机をきれいに片付け、新しい学校に赴任しなくてはなりません。
そのうえで新しいクラスの名簿を作らなくてはならないので、息つく暇もないほど忙しくなるのです。
春休みは、司書も、旧6年の登録を消し、返却されていない本がないかどうか全員分チェックし、公共図書館から借りた本も返却します(うちは、うちにない本をリクエストされたときは借りられるものは公共から借りてきますので)。
うっかりすると6年生が借りたまま卒業してしまうので、これは卒業式までが勝負です。
なかには卒業と同時に引っ越しをなさるお家もあり、引っ越し先から郵送で本が返却されてきたこともありました。
そのあとは新6学年全員分の貸し出しカードを新しく作らなくてはならないので暇ではありません。
なにせ、そのカードを作るのが遅れると、新学期、図書館が開かなくなりますので、これはかなり必死になって作ります。
100人くらいの学校ならそんなに大変ではないのですが、850人の学校に行ったときは本当に大仕事でした。間に合わないかと思った……。
新1年生は割と早めにクラスのメンバーが決まっているのですが、他の学年は変更があるのは当たり前、なので、
あるときなど、ギリギリになって転入生が4人入ってきてクラスが増え、その学年全部作り直しになったこともありました。
ノート形式にして、クラスごとに全員のバーコードを載せてしまえば楽なのですが、うちの学校では公共図書館のように個人カードを持たせています。
カードにしてしまうと手の中で握りしめて破損させたり、落としたり無くしたり、で再発行の手間もかかるようになるのですが、今の校長先生も私も、自分の個人カードを自分で管理できるようになるように教えるのも教育の一環だと考えているので、図書館カードは一人に1枚ずつ持たせるように頑張って作っています。
確かにコンピューター貸し出しが始まった初期の2、3年はかなり再発行した記憶があるのですが、最近は子どもたちもすっかりカードに慣れて管理もうまくなり、ほとんど再発行しなくて済むようになりました。
書架のチェックもこの時期の仕事の一つです。
教科書が変わった年は掲載本も変わるので、各学年の教科書掲載の本をチェック。
掲載本は、棚から抜いて書庫の掲載本の書架に移動(書庫にそういう棚を作ってあるので)。
夏までの季節の展示テーマを考え、必要な本をあらかじめ棚から抜いて集めます。足りないときは、欲しい本を調べ、購入リストに入れます。
入学式用の本の確認もします。
新学期、1番初めの行事が入学式ですが、この時に移動の時間待ちや緊張している子どもたちのために絵本を貸して欲しいと依頼されることが多いのです。
子どもたちも絵本の読み聞かせをしてもらうと落ち着くので、最近の低学年に人気の本を何冊か用意しておきます。
というわけで4月の初めは図書館が無事に開けられる準備が間に合ったらほっと一息、なのですが、そのあとは新しくこられた先生がたに挨拶しながら、学期始まりに必要な本を用意します。
最近は挨拶がわりに本を読まれる先生がたも増えてきました。
先生がたが学習で使う本も依頼があれば、この時に公共に図書館にリクエストしておきます。学期始まりですぐ使いたいという依頼の場合が多いので。
旧1年生から5年生の人たちからもらっていたリクエストの本で公共から借りるものもこのときにリクエストします。
公共図書館へのリクエストは、うちの市では1日何冊まで、という制限があるので毎日少しずつリクエストしなくてはならないのです。
夏休み…… は市町村やその学校によって、司書の雇われ方も仕事の範囲もバラバラです。
まるまる休んでくれ、というところも多いのですが、その一ヶ月は無給になりますので痛し痒しな上に、休みの間にしたい大掃除や書架の移動や本の補修ができない……。
頼むから雇ってくれ、と思いますが、年間何時間、と決まっているところは、夏休みに休まないと、三学期に行く日がなくなってしまったりするのです。
夏休みにほぼ毎日のように開けて子どもたちの勉強をみたり(図書館にはクーラーがあるので涼みにくるのです)イベントやお話会をやっているところもある一方で、プールのある日は図書館も開けてくれ、という学校もあれば、登校日も開けなくていい、というところまでさまざま……。
お金がもらえて休みなら嬉しいのですが、そうもいかないので、夏休みは別の仕事を入れてバイトしている人も多いです。
まとめてみますと
春休みにする仕事
・卒業生の登録削除、新1年生~6年生までの登録、貸出ファイルの準備
・公共図書館への本の返却、リクエスト
・夏までの季節の展示本の用意
・入学式、4月の授業で使う本の準備
になります。
夏休み前にする仕事
夏休みにはたくさん貸し出しします。
特に夏休みに蔵書点検を予定しているところは、夏休み貸し出しは一人10冊とかにしてなるべくたくさん借りてもらいます。
貸した、という記録のある本はあるということになるので、図書館に残った本が少なければ少ないほど蔵書点検は楽になるからです。その貸出のために修理が必要な本を急いで修理しなくてはなりません。
長期休みの前に個人懇談などあって短縮授業になる時があるので、そこで溜まっている修理本は貸し出せるように修理します。
修理の必要な本、というのは人気の本なので、長期貸出には必要なものが多いんです。
ページの破れているところは薄いページヘルパーで、外側のところはブッカーで補修します。
破れてもセロテープで直さないでください、という放送を毎月したおかげて、いまは、破れたページは、はさんでくださるようになりました。
セロテープは1年もたずに劣化して茶色に、モロモロになってしまうので、まずそれをはがさなくてはならず、貼られてしまうと3倍くらい時間がかかり、厄介なのです。
もう修理不可能な本は、廃棄にし、登録を外してリストを作ります。うちの学校では、そのリストを校長先生が許可してくださると、捨てられることになっています。
学期ごとに先生達のための図書館通信も作成して、終業式前日に配布していました。
お休みに入ると来られない先生がたもいらっしゃるので。今学期、今年度、図書館ではこんなことをしましたっていうことを報告しないと、先生がたには知ってもらえません。
特に他の学年のことまでは、ご存知ない先生が大多数です(全体を把握してらっしゃるのは校長先生と副校長先生くらいです)。
この通信をだし始めて、ようやく先生がたに、図書館がなにをやっているのかを理解していただけるようになりました。
この通信が、一番反応があります。 各学年ごとの貸し出し冊数や使い方状況も載せるので「ぼくらの学年の子どもたちは、図書館を上手く利用してますね!」とか「他の学年がやってたように○年生も秋学期は図書館で調べ学習したい」とか「二年生がやってもらった、この“目次と索引”の授業を3年にもやってください」とか。
これを作るようになってから、図書館、宣伝大事!と思うようになりました。
みなさん自分のクラスがありますから、気にはなっても、他学年の授業なんて見るチャンスすらないのです。 普通の会社なら、自分の部署がなにをしたかの報告書は必ず上に出すでしょう。最初は子どもたちに出すのとは別に、先生がたにも何をしたか知らせたほうがいいだろうなぁ、くらいの軽い気持ちで始めたのですが、それに先生がたがびっくりするほど反応してくださったので、反省……。
図書館は、図書館としての報告書、すらだしていなかったのですから。
というわけでいまは真剣に、力を入れてだしています。
夏休みの開館日の準備
貸出期間や開館日の相談を司書教諭の先生に確認します。また、夏休み貸出期間の開始日や冊数も臨時の図書館だよりをだして、子どもたちにもお知らせします。中には宿題で借りたい本を貸出開始日に借りにくる子がいるので……。
私が勤務した学校では、今借りているものを全部返却すれば夏休み貸出ができることにしていました(なるべく学期内に借りた本は一度返却してもらうように)。
学期をこえると、みんな本がどこにいったかわからなくなるということがわかったので。
さあ、夏休みがんばるぞ!と気合もいれます。
2025/09/11 更新