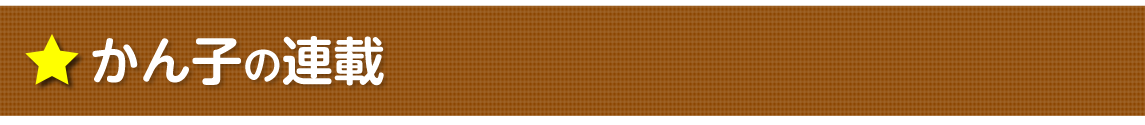☆楽しい学校図書館のすぐに役立つ小話☆彡【司書は椅子に座ってピッとやるだけの人じゃありません。学校司書は忙しいんです。・4-7<最終回>】
昨年よりご紹介してきました『司書は椅子に座ってピッとやるだけの人じゃありません。学校司書は忙しいんです。』もなんと今回が最終回となりました。
桜李桃梨(おうりとうり)さん、忙しい中毎月寄稿頂き本当にありがとうございました。
それでは、学校司書さんの忙しいお仕事の最終回、ぜひご覧ください!
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
4-7 長期休みの間の仕事 ②夏休みから
夏休み
夏休みにする仕事は普段できない、書架や図書館全体の点検と大掃除です。
ペンキが剥がれていたり、壁紙が破れていたり、木枠が壊れていたり、椅子のネジが飛んでいたり、カーペットに染みができていたり……。
普段も、破損や汚れを見つけたら、もちろんすぐに修理したり、掃除したりして対応しているのですが、それでもチェックするといろいろ出てきます。
ペンキを塗り直した書架も下の段、は本でこすられるのでやっぱり剥げてきます。
やっぱり人気の本が入ってる書架は出し入れが多いので、下地が見えるくらい剥げています。
全体も3年に一度は塗り直したい。
塗るときは、塗り直す棚の本を全部取り出して、塗らない書架にはゴミ袋などで養生します(あ、養生、というのは、ペンキが飛んでも大丈夫なように、何かでカバーすることです。ホームセンターに行けば、養生テープという便利なものも売ってます)。
そうして、塗り直すところだけどんどん塗っていきます。
学校は、使える塗料が決まっているので(子どもたちに影響のないものを用務員さんがたいてい修繕用に持っています。もしなければ、副校長先生に相談して、一年で使うだろうなぁという量を計算して年度始めに図書館用に購入してもらっています)事前に用意します。
素人でも、3回塗るとムラがなくなりますからご安心を。塗料に余裕があれば、館内や図書館前の廊下などの壁も塗り直します。
そうすると、いっきに館内も廊下も明るくなるんです!
最初にペンキを塗り始めた時は、本当にドキドキでしたが、塗ったら思わずほうっ!と声がでたほど明るく見違えるようにきれいになったので、すっかりはまり、そのうち慣れてくるとあちこち気になるように、というか、汚れが見えるようになりました。
大人は情報選別能力が高いので、脳がいらない、と判断すると目の前で見ているのにその情報は捨てられてしまう……意識して見ようとしないと見ているのに見えないのだそうです……。
私も塗るようになって、ようやく、壁が汚れていることが見えるようになりました。
その後、たまたま通りかかった理科専科の先生に図書館前の廊下の壁を塗ってるところを見られて
「すごいね!塗るだけでこんなに明るくなるんだ!」とたいそう褒めていただき「どうやるの?」
と聞かれて塗りかた(まず塗りたい壁を雑巾で拭いてホコリを除去しておく。そのあと塗る壁の周り、床を養生して塗ること)もお伝えしました。
その後、その先生も取り掛かられたようで、突き当たりの、どっちかというと暗めの廊下にあった理科室の周りがいきなり明るくなりましたっ!
(この作業、最初は全部ひとりでしていたのですが、ペンキ塗り前の雑巾で壁を拭くのは大掃除の時にお掃除メンバーにしてもらうようにしました。みんなでやれば一瞬なのと、普段やらないことをするのは楽しいようで、大喜びでやってくれます)
普段仕事しながら気づいたことはメモしておいて、あとで対処するのですが、気をつけていても汚れは忍び寄ってくるのです。
電気のスイッチのところとか、黒板の上の縁とか、書架の一番てっぺんの板とか、思いのほか汚いです。
天井と平行になっているところには埃が積もる、と教わってから(考えれば当たり前のことなんですが)平行になっているところを意識して探すようになりました。
学校の壁には抽象的な模様とかが、左官屋さんがやるコテ細工のように彫られていたりしますよね。
カッコいいですが、あれもめっちゃ汚いです。
あるときたまたま雑巾を持っていたもので、考えなしに何気なく一箇所を拭いたところ色が変わり……ひえっ、となりました。
結局脚立に乗って全部磨きましたが、高圧洗浄機、欲しかったです。
15年、掃除してなかったのでかなり手強かったです。
でも本当に壁の色が変わり、そこも明るくなりました。
できたときは、こうだったんだなぁ、でした。
次はカウンター周りの点検です。
図書館は紙ゴミが溜まりやすいので、ときどき徹底的に整理しないとすぐに紙がうず高く積もってしまいます。
まずは紙を整理して、要るものはファイリングし、いらないものは捨てます。
整理棚とかも買えないので結局段ボール箱頼りになりますが、段ボールも段ボールのままで使わず、きれいな布や、紙、を貼ると片づいて見える! というのを発見してからは、せっせと“入れるところ”を作っています。 学期のあいだはその箱のなかに放り込んでおいても、外からは乱雑に見えないし、整理するときもその箱ごとにすればいいので、このやり方にしてから、かなり楽になりました。
この箱もやはりただの段ボールですから、3年も使うと傷みます。
なので、新しい段ボール箱を作ります。
紙よりも布のほうが品よく仕上がるのと、丈夫なのと、紙より布のほうがデザインが豊富なので、私は布を貼っています。
いくらカウンターの下でも見えることは見えるので、図書館全体のデザインに合うものを選びます。
カウンター自体もかなり汚れているので、上に乗っているものを全部どかし、天板は洗剤とメラミンスポンジを使って磨きます。
特に小学校は、鉛筆の粉で半端なく汚れますから。
引き出しのなかも整理し、
引き出しそのものも引き出して洗って磨き、美しくなった段ボールをカウンターの下に設置して完了……。
以前行った小学校では、あまりにもカウンターが汚かったので、夏休みに天板にジーンズ生地を貼り、縁だけ、ペンキを塗りました(これは用務員さんの意見、というか助力により、鋲を打って布を止めました。鋲自体がデザインになって、とてもカッコよく仕上がりました😁)。
図書館自体がきれいになったら、次は本の番です。
棚を点検して、情報が古くなって、これはもう使うのはちょっと、という本はカウンターの後ろの棚に一旦置きます(オープン書庫、と呼んでます)。
3年使わなかったら廃棄対象にします。
うちの図書館助手、カエルのぬいぐるみ、ピクルスも洗います。
どうしても人気者は薄汚れてきちゃうので、背中の縫い目を少しほどき、中身は出して天日干しに(中身が足りなくなっていたら、入れる時に足します)。外側は洗って乾かします(ぬいぐるみごと自宅のお風呂で洗うやりかたもありますが、こちらのほうが簡単でよく乾きます)。
そしてまた中身を入れたあと縫い直します。学期始まりや学年始まりはピクルスを見て「きれい!フワフワ」と堪能される方が毎回いらっしゃいます。 その時期は特に触って癒されることが大事なので、ふわふわピクルスは重要……きれいなピクルスが必要なんです。 以前いた学校では、落ち着かない子のために学年始まりに教室にピクルスが出張に行ったこともありました。物を擬人化することが得意な日本人には、ぬいぐるみはすごく効果的です。特に低学年には……。
いつも穏やかに笑っているピクルスを見ると、みんな落ち着いて静かになるのです。高学年でも!
冬休みにする仕事
・夏休みと同じく書架や図書館全体の点検
・ピクルスの洗濯
・季節の本の用意・確認
・公共図書館へのリクエスト(学習で使う本・子どもたちのリクエストの本)
年度末には来年度購入する本のリストを作ります。
学年始まりのある時ちょっとひきつった顔をした子が図書館に駆け込んできて、どうしたんだろうって思ってそっと見てると
「あーここは空気が変わらないわ!落ち着く!」と言われました。
そうなんです!
子ども達は、学期や学年始まりにクラスの友達や担任の先生や教科の先生が変わったり、転入生や行事などの変化にドキドキしているんです。
だからこそ居心地の良さが変わらない図書館って大事だと思います。
学校司書って、椅子に座ってピピっとしているだけじゃないんですよ。
は~。
さぁ、明日もがんばろうっと!
2025/09/25 更新